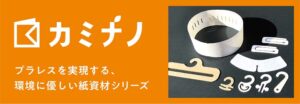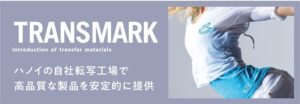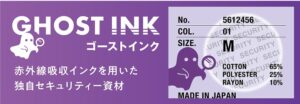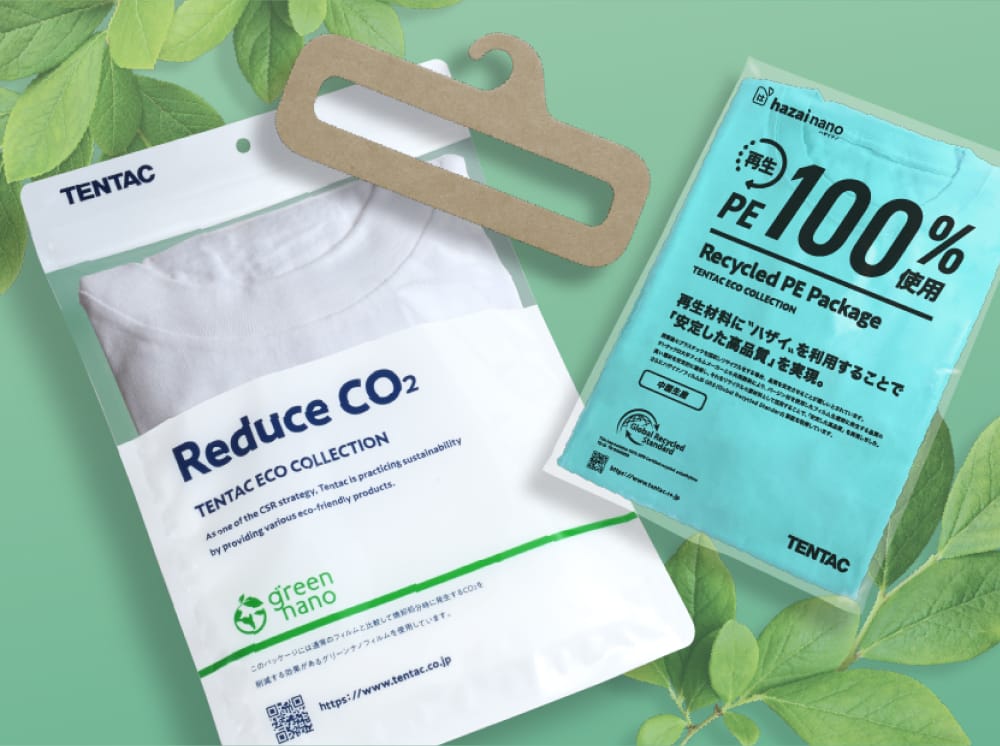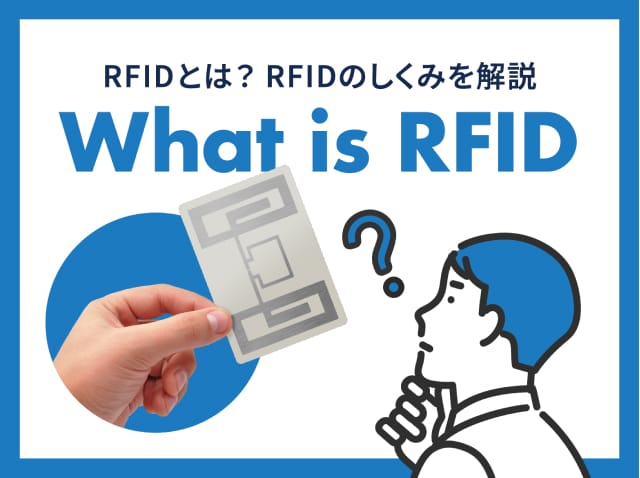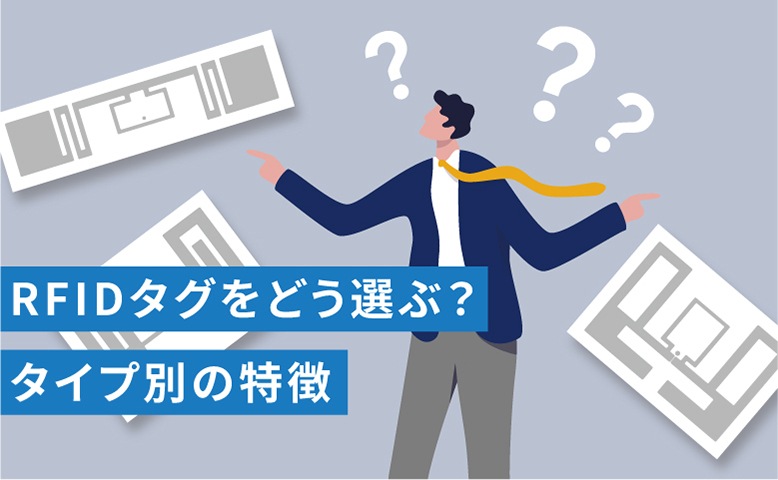Contents
RFIDとは?基本の仕組みと動作原理
RFIDの構成要素(タグ・リーダー・管理システム)
RFID(Radio Frequency Identification)は、電波を利用して対象物の情報を非接触で読み取る自動認識技術です。基本的な構成要素は「RFIDタグ」「リーダー」「管理システム」の3つです。
• タグ:対象物に取り付けられたICチップ内蔵の識別子。内部にIDや属性情報が記録されており、リーダーから送られる信号に応答します。
• リーダー:RFIDタグから情報を読み取る装置。固定型、ハンディ型、ゲート型など運用に応じた種類があります。
• 管理システム:読み取った情報を収集・保存し、在庫管理や工程管理などに活用します。
この3要素が連携することで、目視確認や手作業を大幅に削減でき、業務の効率化と情報精度の向上が期待されます。
非接触通信と一括読み取りのしくみ
RFIDの大きな特長は、電波による非接触通信と複数データの一括読み取りです。リーダーから発信された電波にタグが反応し、IDなどの情報を返送します。この処理は視認不要で、遮蔽物があっても一定条件下で読み取り可能です。
また、1対1の読み取りが必要なバーコードとは異なり、RFIDは複数タグを同時に認識できます。これにより棚卸・入出庫・検品などの作業時間を大幅に短縮でき、人的ミスの削減にもつながります。
RFIDタグの種類とその特徴
パッシブタグ・アクティブタグ・セミアクティブタグの違い
RFIDタグは大きく分けて「パッシブタグ」「アクティブタグ」「セミアクティブタグ(バッテリーアシスト型)」の3種類があります。それぞれのタグは電源の有無や通信距離、用途によって使い分けられています。
パッシブタグは内部に電源を持たず、リーダーから発せられる電波を受けて動作します。そのためタグ本体は非常に薄く軽量で、コストも低く抑えられるのが特長です。読み取り距離は数cm~数m程度で、商品管理や在庫管理など、短~中距離の用途に適しています。
一方、アクティブタグは内蔵バッテリーを使って定期的に信号を発信するため、より長距離の通信が可能です。読み取り距離は数十メートル以上に及び、輸送中の資材管理や大型設備の位置追跡など、広範囲の監視が求められる用途に向いています。
セミアクティブタグは、基本的にはパッシブ動作をしながら、通信時のみバッテリーを使用する仕組みです。パッシブタグよりも読み取り精度が高く、アクティブタグよりも消費電力を抑えられるため、バランスの良い中間的な選択肢として用いられます。
タグの構造とデータ記録方式
RFIDタグは、ICチップ・アンテナ・台紙やカバー材などで構成されています。ICチップには個体識別情報(ID)やその他必要な情報が記録されており、アンテナがリーダーからの信号を受信・送信する役割を担っています。タグの外装材は、使用環境(高温・金属周辺・屋外等)に応じて選定され、耐久性や柔軟性が考慮されます。
また、データ記録方式には「リードオンリー」「ライトワンス」「リードライト(書き換え可能)」の3種類があります。リードオンリータイプは出荷時にIDが書き込まれており変更できません。ライトワンスタイプは一度だけデータを書き込み可能で、製造・検品後の追跡用途などに用いられます。リードライトタイプは必要に応じて何度もデータの書き換えができるため、メンテナンス履歴や工程進捗など、変化する情報の記録に適しています。
このように、タグの種類や構造、記録方式は、導入目的や運用環境によって最適な選択が異なります。導入前には使用条件をしっかり整理し、現場に適したタグ仕様を選定することが重要です。
RFIDの通信方式と周波数帯
LF・HF・UHF・マイクロ波の特徴と使い分け
RFIDは使用する周波数帯によって、「LF(低周波)」「HF(高周波)」「UHF(超高周波)」「マイクロ波」の4種類に分類されます。それぞれに通信距離・読み取り速度・干渉の影響といった特性があり、用途や設置環境に応じた使い分けが必要です。
• LF(125〜134kHz)
通信距離は短く(数cm〜10cm程度)ですが、金属や水の影響を受けにくいため、動物管理や自動車のキー認証などに使われます。通信速度は遅めですが、安定性重視の用途に適しています。
• HF(13.56MHz)
通信距離は10〜30cm程度。非接触ICカードや図書館の蔵書管理、医療現場での機器管理などに幅広く利用されています。コストと性能のバランスがよく、消費電力も低いため、流通分野でも人気があります。
• UHF(860〜960MHz)
数m〜10m程度の通信距離があり、一括読み取りや高速通信が可能です。在庫管理、物流、製造ラインなど大量タグの読み取りが求められる場面で広く活用されています。ただし、金属や液体に弱い点があるため、使用環境に注意が必要です。
• マイクロ波(2.45GHzなど)
高速通信が可能で、ゲート通過時の読み取りや車両通過管理などに用いられます。通信距離は短め〜中程度で、価格や環境への影響を考慮する必要があります。
周波数による適用シーンの違い
RFIDの周波数帯ごとの特性を理解することで、導入対象業務への適切な選定が可能となります。たとえば、病院の資産管理には金属や液体に強いHF帯および金属や液体に対応したUHF帯が適しており、一方で倉庫内の在庫一括読み取りにはUHF帯が最適です。
また、国や地域によって使用可能な周波数帯に制限があるため、グローバル展開を視野に入れる企業はその点も考慮する必要があります。実際の導入に際しては、現場環境・業務内容・制度要件の三点から、最も適した方式を選定することが成功への鍵となります。
バーコードとの違いと使い分けの考え方
読み取り方式と速度の違い
RFIDとバーコードはどちらも物品の識別や管理に使われる技術ですが、その仕組みには大きな違いがあります。バーコードは光学的に印刷されたコードをスキャナーで読み取るのに対し、RFIDは電波を用いて非接触でタグ情報を取得します。
この違いにより、読み取り速度や作業効率に大きな差が生まれます。バーコードは基本的に一つずつスキャンする必要がありますが、RFIDは複数のタグを一括で高速に読み取ることが可能です。これにより、棚卸や入出庫の作業時間が大幅に短縮され、人為的な読み取りミスも減らすことができます。
また、RFIDは視認性に依存せず、箱の中や視界に入っていない位置でも読み取れるため、作業者の負担も軽減されます。
コスト・精度・導入規模での比較
一方で、バーコードは導入コストの低さが大きなメリットです。印刷費用が安価であり、専用設備が少なく済むため、小規模な運用や一時的な利用には適しています。RFIDはタグやリーダーなどの初期投資が必要で、一定の導入コストがかかりますが、その分、長期的な運用効率や正確性において優れた効果を発揮します。
精度の面では、RFIDは読み取り漏れが少なく、個体ごとの識別や情報の書き換えが可能な点で優位です。ただし、金属や液体などの環境要因による電波干渉には注意が必要です。
つまり、バーコードとRFIDは「どちらが優れているか」ではなく、「用途や目的に応じて使い分ける」ことが重要です。たとえば、大量の在庫を迅速に処理したい場合はRFIDが適しており、簡易的な管理にはバーコードが適しています。現場の業務フローや管理対象の性質を踏まえた最適な選択が、業務効率を大きく左右します。
RFID導入前に押さえておきたい注意点
設置環境と読み取り精度への影響
RFIDの性能を最大限に発揮するためには、設置環境と読み取り精度の関係を正しく理解しておくことが重要です。RFIDは電波を利用するため、周囲の金属・液体・高温環境などに影響を受けやすく、設置場所やタグの貼付位置によって読み取り精度が大きく変動します。
たとえば、金属部品に直接タグを貼り付けると、電波が乱反射して読み取りに失敗するケースがあります。このような場合には「金属対応タグ」や「スペーサー」を使用する必要があります。また、水分を多く含む食品や液体商品に対しては、UHF帯の読み取りが不安定になることがあるため、金属や液体に対応したタグか、HF帯を選択するなど、使用周波数の調整も求められます。
さらに、読み取りリーダーの設置場所や角度、読み取り範囲(アンテナの指向性)も考慮が必要です。特に複数のタグを一括で読み取る場合は、タグ同士の干渉(コリジョン)や読み漏れを防ぐために、リーダーの位置や照射範囲をシミュレーションしながら設計することが欠かせません。
タグ・リーダーの選定と運用設計のポイント
RFIDの運用設計においては、タグとリーダーの選定が成否を左右する重要な要素です。タグにはさまざまな種類があり、「パッシブタグ」「アクティブタグ」「セミアクティブタグ」などが代表的です。これらは電源の有無や通信距離、価格に違いがあり、用途に応じた選択が求められます。
たとえば、短距離かつ安価に大量運用したい場合はパッシブタグが適していますが、広範囲でリアルタイム追跡を行いたい場合はアクティブタグが有効です。また、タグのサイズや貼付方法、耐熱・耐水性といった仕様も、現場の条件に合わせて検討する必要があります。
一方、リーダーも据え置き型やハンディ型、ゲート式などがあり、読み取り対象物のサイズや移動状況、設置スペースに応じた選定が不可欠です。さらに、読み取ったデータを管理システムへどのように連携させるか、既存の業務フローにどう統合するかといった運用設計の検討も重要なポイントです。
事前に現場環境や使用目的を明確にし、段階的に運用テストを行いながら仕様を固めていくことで、導入後のトラブルや想定外の運用負荷を防ぐことができます。
テンタックのRFIDソリューション支援
業種・用途別に対応する提案力
テンタックは、製造・物流・小売など多様な業界におけるRFID導入支援に実績を持つ企業です。各業界・現場ごとに異なる運用課題や制約に対応するため、業種や用途別に最適化されたタグやリーダーの選定、読み取りポイントの設計など、柔軟かつ実践的な提案を行っています。また、難易度の高い環境条件にも対応できる知見を活かし、単なるRFID機器の提供にとどまらず、現場での活用を見据えた提案が可能です。
導入から運用定着までのサポート体制
テンタックの支援は、導入前のヒアリング・要件整理から始まり、試験導入・本導入・定着支援までを一貫してカバーしています。単発的な納品で終わらせず、導入後も定期的な効果検証やシステムアップデートの提案を行うことで、長期的な運用安定と成果の最大化を支援します。
また、RFIDの活用を初めて検討する企業に向けて、現場訪問や無料相談を通じた初期サポート体制も整備しており、「何から始めればよいかわからない」という段階からの伴走が可能です。
まとめ|RFIDの基礎理解が導入成功の第一歩

RFIDの導入を成功させるためには、まず「正しく理解すること」が欠かせません。タグの種類や構造、通信方式や周波数帯の違いを把握することで、自社の運用に適した選択が可能になります。また、バーコードとの違いを踏まえたうえで、どの業務にどの技術が適しているのかを判断する視点も求められます。
さらに、設置環境や読み取り精度への影響、運用設計の重要性など、導入前に押さえておくべき注意点も少なくありません。こうした基礎的な知識をしっかりと身につけることが、導入後のトラブルを回避し、現場に定着させるうえでの第一歩となります。
テンタックでは、用途や業種ごとのニーズに応じた提案から、導入・運用の定着支援まで、専門的な知見と経験をもとに丁寧にサポートしています。RFID導入を検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。現場の課題に寄り添った最適なソリューションをご提案いたします。