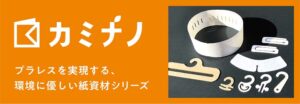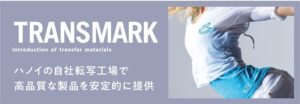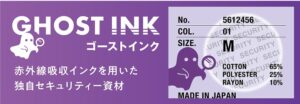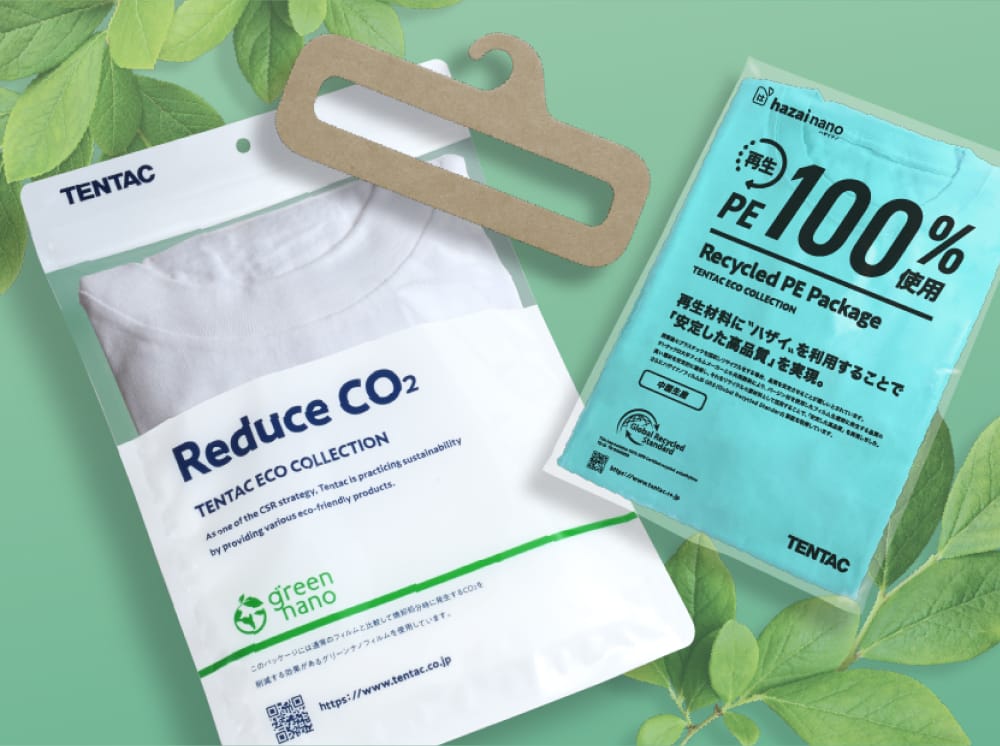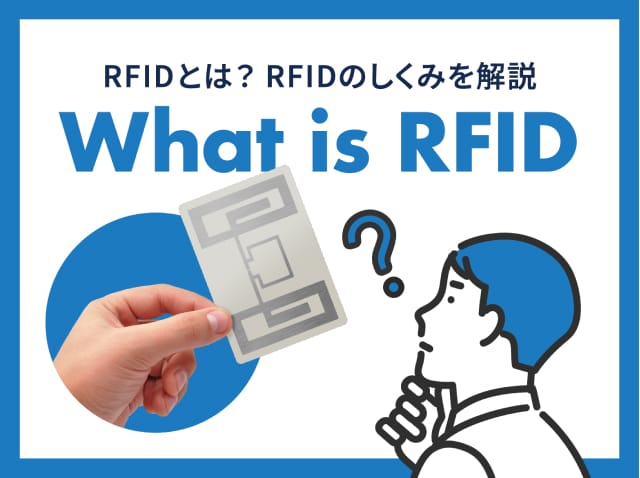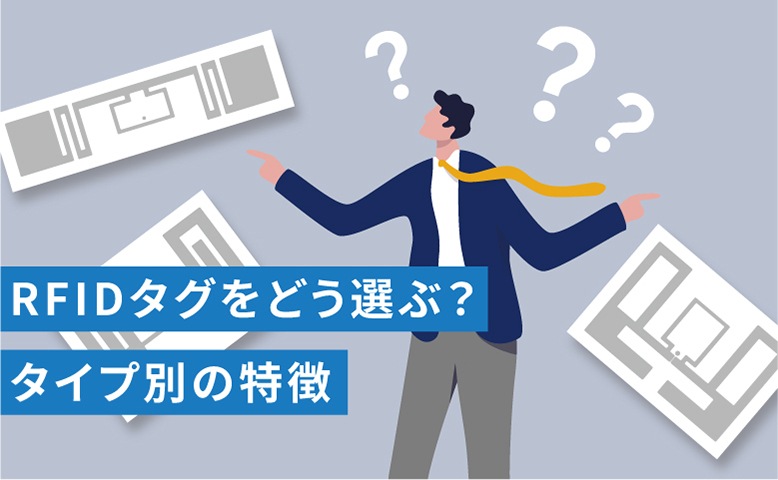Contents
ICタグ(RFタグ)とは?仕組みの基本を押さえよう
ICタグは何をしているのか?基本構成と役割
ICタグ(RFタグ)は、RFIDシステムにおいて情報を保持し、リーダーからの信号に応じてその情報を応答する「情報の器」ともいえる存在です。主に「ICチップ」「アンテナ」「台紙(基材)」の3つの要素で構成されており、それぞれが連携することで非接触かつ高速な情報通信を実現します。
ICチップには、製品番号や管理情報などのデータが記録されており、この情報は読み取り専用のものもあれば、必要に応じて書き換え可能なタイプもあります。タグの形状や素材は用途に応じて多様で、物流、医療、製造など幅広い分野で活用されています。
アンテナとICチップの関係|電波の受信とデータ通信
アンテナは、ICタグがRFIDリーダーからの電波を受信し、それに応答するための重要な役割を担っています。リーダーから発信された電波をキャッチすることで、ICチップに電力を供給し、内蔵されたデータを応答信号として返す仕組みです。特にパッシブタグの場合、外部電源を持たないため、アンテナからの電波受信が通信の起点になります。
アンテナの形状や大きさは、通信距離や応答速度に影響します。たとえば、読み取り距離を重視する場合は大きめのアンテナが採用され、小型機器への内蔵用途ではコンパクトなアンテナが用いられます。ICチップとアンテナが一体となって機能することで、RFID通信の基本的なやりとりが可能になるのです。
ICタグの構造を構成要素ごとに解説
ICチップの内部構造と格納データの種類
ICチップは、ICタグの中でもっとも重要な部分であり、データの記録と処理を行う役割を担います。内部には「メモリ」「ロジック回路」「電源制御回路」などが組み込まれており、用途やタグの種類によって構成が異なります。
格納されるデータには、製品IDや出荷日、ロット番号などがあり、一部の領域にはユーザーが書き込みを行えるものも存在します。セキュリティ機能を備えたICチップでは、読み取りや書き込みにパスワード認証が必要な場合もあります。これにより、不正な読み取りや改ざんのリスクを軽減できます。
アンテナの形状と材質による特性の違い
アンテナは、リーダーとの通信品質に直結する重要な要素であり、設計次第でタグの性能が大きく変わります。アンテナの形状には、ループ型、ダイポール型、スロット型などがあり、使用する周波数帯や用途に応じて最適なデザインが選ばれます。
材質としては、一般的にアルミニウムや銅が使われますが、柔軟性や耐環境性が求められる場合には、銀インクなどの印刷型アンテナも採用されます。さらに、基材との相性や取り付け面(段差、金属、曲面など)との関係も考慮する必要があります。アンテナ設計は、読み取り範囲や方向性だけでなく、電波干渉を最小限に抑えるためにも繊細な調整が求められます。
通信方式の違いによって変わるタグの仕様
周波数帯と読み取り距離の関係(LF/HF/UHF)
ICタグは使用する周波数帯によって通信特性が異なります。代表的なのが「LF(低周波)帯」「HF(高周波)帯」「UHF(超高周波)帯」の3種類です。
「LF帯(125kHz前後)」は通信距離が数センチ程度と短く、金属や水分の影響を比較的受けにくいのが特徴です。動物の個体管理や入退室管理など、至近距離で確実に読み取りたい用途に適しています。
「HF帯(13.56MHz)」は通信距離が10〜30cm程度で、NFCとの互換性があることから、交通系ICカードや図書館管理などにも多く採用されています。読み取りの安定性とコストバランスに優れた帯域です。
「UHF帯(920MHz前後)」は数メートルから10メートル程度の読み取りが可能で、一括読み取りや移動体の検知に強みがあります。物流や倉庫、アパレルの在庫管理といった大量読取・中距離通信を要する現場で活躍しています。
導入現場の通信距離や障害物の有無によって、最適な周波数帯を選定することが重要です。
パッシブ/アクティブの違いと動作原理
ICタグは電源の有無によって「パッシブタグ」「アクティブタグ」「セミアクティブタグ」に分類されます。
「パッシブタグ」は内部に電源を持たず、リーダーから送られた電波をエネルギー源として起動・応答します。構造がシンプルで小型化しやすく、低価格での大量導入に向いています。一方、通信距離は比較的短く、読み取り環境に影響を受けやすい側面もあります。
「アクティブタグ」は内蔵バッテリーを搭載しており、自ら信号を発信することができます。読み取り距離が長く、通信の安定性に優れているため、高価な設備や長距離追跡用途に最適です。例えば、建設機械や車両の位置管理、資産管理などに使用されます。
「セミアクティブタグ」は通常はスリープ状態で待機し、リーダーからの電波を受けたときだけバッテリーを使って応答する仕組みです。アクティブとパッシブの中間にあたるタイプで、バッテリー寿命と通信距離のバランスを取りたい場合に有効です。
システムの規模や利用頻度、運用コストに応じて、タグの電源方式も重要な選定ポイントとなります。
用途や環境で選ぶ|タグタイプの使い分け
シール型/カード型/リストバンド型などの活用例
ICタグは設置場所や対象物に応じて、形状も多様に展開されています。
最も一般的なのが「シール型(ラベル型)」で、商品や梱包材などに直接貼付する用途に適しています。薄型で軽量なため、アパレルや物流現場などで広く活用されています。
「カード型」は社員証や入退室管理など、携帯しやすさや視認性を求められるシーンに用いられます。耐久性があり、ICチップ以外の情報(氏名や顔写真など)を印刷することも可能です。
「リストバンド型」は病院やイベント会場など、個人単位での一時的な識別に使われます。耐水性や装着性を重視した設計がされており、装着者が動いてもタグが安定して読み取れる工夫が施されています。
このほか、ネジ止めできるハードケース型や、ケーブルに巻き付けるタイ型など、特殊形状のタグも多く存在し、管理対象物に応じて柔軟な選定が可能です。
高温・金属・水回りなど特殊環境への対応構造
ICタグは読み取り精度に影響を及ぼす周囲の環境に応じて、構造面でも工夫が必要です。
たとえば、金属面に貼り付ける場合、通常のタグでは電波が乱反射し通信不良が起こることがあります。そのため「オンメタルタグ」と呼ばれる、金属反射を防ぐ専用設計のタグが用いられます。絶縁層を持たせたり、アンテナ構造を工夫することで、安定した読み取りが可能になります。
また、高温下での使用が想定される製造業では、耐熱樹脂を使用したタグが必要です。数百度に達する焼成工程や金属加工現場でも耐えられるように、タグ素材や封止構造に工夫が凝らされています。
水分の多い環境、たとえば食品工場や病院などでは、防水・防湿性能が求められます。こうした環境に対応したタグには、密閉構造や防滴ケース、抗菌仕様などが採用されています。
使用環境に適したタグ構造を選ぶことで、読み取りの安定性と運用の信頼性を高めることができます。
ICタグの性能を左右する「設計の工夫」
読み取り距離や精度に影響する物理設計要素
ICタグの性能は、使用する周波数帯や通信方式だけでなく、タグ自体の物理的な設計にも大きく左右されます。とくに「アンテナの形状・寸法」「チップとアンテナの接合位置」「台紙素材の選定」といった要素は、読み取り距離や精度に直結します。
たとえば、UHF帯のタグではアンテナの長さと形状が通信距離に大きな影響を与えます。広範囲の読み取りを可能にするには、一定のサイズを確保し、指向性と感度を最適化する必要があります。一方で、タグの貼付対象が小さい場合は、サイズ制約の中で最大限の性能を引き出す設計が求められます。
また、ICチップの配置位置やアンテナとの結合状態も重要です。微細なズレや接触不良が読み取り不良の原因となるため、製造工程の精度や接着材の選定にも工夫が必要です。
さらに、台紙や保護フィルムに使われる素材によっても電波の透過率が変わるため、現場環境に適した材質選びが読み取り安定性を左右します。とくに高温や湿度変化の大きい環境では、長期使用による劣化も見据えた設計が求められます。
テンタックの設計技術と現場適応ノウハウの紹介
テンタックでは、こうしたICタグの物理設計に関する知見をもとに、お客様の使用環境や管理対象に応じた最適なタグ仕様をご提案しています。
たとえば、物流や製造現場で使用される大量の箱や金属製資材に対しては、オンメタル仕様や耐久性の高いアンテナ設計を採用。また、タグサイズに制限がある場面では、独自の小型アンテナ設計技術により、限られたスペースでも確実に通信できるよう対応しています。
さらに、テンタックは現場ごとの運用フローを丁寧にヒアリングし、タグの貼付位置や読み取り方法、運用上の注意点までを含めたトータル設計支援を行っています。PoC(試験導入)を通じて実地検証を重ねることで、理論値ではなく「現場で使えるタグ」の提供を重視しています。
こうしたカスタマイズ対応力と現場適応ノウハウが、多様な業種でのRFID導入を支えています。
まとめ|構造を理解することが最適なタグ選定への近道

機能を知ることで導入後の失敗リスクを回避
ICタグの導入は、単に「読み取れればよい」というものではありません。用途に合ったタグを選ばなければ、通信エラーや運用トラブルの原因となり、結果として業務効率の低下や再設計の手間が生じることもあります。
ICチップの仕様、アンテナ設計、タグ形状、周波数帯といった構造的な要素を理解することで、導入時のリスクを事前に把握し、より的確な選定が可能になります。
構造と用途をセットで理解し、自社に合った製品選定を
タグの構造的な違いと、それぞれがどんな現場で効果を発揮するのかをセットで理解することが、RFID活用の第一歩です。特に、タグが使用される環境(温度、湿度、金属の有無)や管理対象(サイズ、材質、運搬形態)に応じた選定が、運用成功の鍵を握ります。
テンタックでは、製品の構造的な理解を深めていただくための技術資料やPoC支援も行っております。導入後に「思っていたように使えなかった」と後悔しないためにも、初期段階から丁寧な情報収集と相談を重ねることをおすすめします。